総合学習もどきの例(面白半分版)
(注)前半は固い文章です。後半は無責任な文章です(^^;)
書いた時点(平成10年8月末)の話題等を扱っているので、あとで
読んだ場合には、わかりにくい部分や的はずれな表現があるかも知れ
ません。
平成14(2002)年度から実施される「完全学校週5日制」にむけて、平成10年7月29日に教育課程審議会の答申が発表された。
その中でも特徴的なのが、小中高で実施される「総合的な学習の時間」である。
○ 各学校の創意工夫を生かした
○ 横断的・総合的な
○ 自ら課題を見つけ
○ 自ら学び、自ら考え、主体的に判断し
○ よりよく問題を解決する資質や能力を育てる
○ 試験による数値的な評価は行わない
などのキーワードが並べられた、この「総合的な学習の時間」は、「生きる力を育む」という次期教育課程の精神を最も具現化したものであるという趣旨はわかるものの、具体的にはどういう活動をするのかという姿がなかなか見えてこない。
「国際理解」「情報」「環境」「福祉・健康」など、いわゆる現代的課題と呼ばれるものを扱いながら、「社会の変化への主体的な対応力」を育てる、(教科等の)横断的・総合的学習というように表現されているのだが、それは教科書に書いてあることを読むような全国共通のものではなく、その学校や地域の実態や特色を生かして行うとされているので、全国どこでも通じるような一般的な例は示しにくい。校長の学校経営の姿勢や、研究主任の頭脳と手腕が問われることになろう。
と、まあ、難しいことを書いてみたが、要は、これまでの教科にしばられた知識の詰め込み(およびその定着具合を見るためのテスト)にこだわらない「自由で面白い」活動をやっていく中で、「面白がって、いろんなことを調べたり考えたり、ちょっと難しそうなことにも自分の力で挑戦してみようとする子供」を育てるという学習指導だと考えれば良いようである。(そういう子供が少なくなってきているという現実をふまえた提言であろう)
しかも、それは、算数とか国語とかの教科に限定しない活動で、1つのテーマを解決するために、それまで学習したいろんな教科の学習内容や能力を使い、さらに点数化された成績がつかないというのだから、やりようによっては、教師にとっても子供にとっても、すごく楽しい活動ができる可能性を持っている。
これが全くの目新しい学習活動かというと、そうでもない。このような活動を、これまでも無意識のうちに行ってきていたのではないだろうか。
例えば、修学旅行。
子供たちの手で「修学旅行のしおり」を作るところも多いようだ。その際に見学地のデータを調べてまとめるという活動をする。地理的なことや歴史的なことを調べるのは社会科の学習の要素が大きい。絵を描いたり、文章にしたりするのは図工科や国語科だ。
グループ別自由行動をするなどというときには、時刻表を調べてタイムテーブルを組んだり、移動距離を調べてタクシーの料金を計算するなど、算数の力を使うことになる。
全部の活動について述べるとくどくなるので、この程度にするが、いろいろな活動は、全て「思い出に残る、楽しい修学旅行にしよう!」という大きなテーマに結びついており、この活動の中で、子供たちは「生きる力」を身につけ、成長する。
修学旅行が終わった段階で成績をつけることはない。(「君は集合時刻に遅れたから『2』!」とか、「お小遣いの約束を守って上手にお土産が買えたから『5』!」なんてことを教師が言ったら艶消しも甚だしい)教師が点数をつけなくても、修学旅行の思い出は、それぞれの子供の心に残るはずである。
思ったように活動できなかったり、何か失敗をしてしまったりして、苦い思い出が残っても、「でもやっぱり友達と一緒に行った修学旅行は、私にとって忘れることのできない楽しい思い出です」と、その子が感じたら、それはそれで素晴らしい自己評価だし、それ以上のことを教師がどうのこうの言う必要はない。
「こんなのも総合学習だよ」という例が長くなってしまったが、修学旅行は学校生活で一度しかない大きなイベントだし、教師のほうでも、特例として、教科の学習の時間をつぶして、準備のための時間を確保してあげたりするので、「総合的な学習の時間」の例としてあげるには一般的ではないかもしれない。
実際に、時間割上に位置づけて実施するのは2002年になってからでよいのだが、それまでのうちにいろいろと試行して、「総合的な学習の時間」についての準備を進めておかなければならない。
そこで、たった1時間ででき、「総合的・横断的」という要素を十分採り入れた、「面白半分バージョン総合学習」の例を発表(^^;)する。
「面白半分」という冠がついている通り、まじめに「国際理解」だの「環境問題」だのに取り組むようなものではないのだが、子供たちにむりやり計算や資料調べをさせるのではなく、子供自身の興味関心のもとに(実際は、そう思いこませて)、算数科や社会科の(かなり難易度の高い)学習を組み合わせた活動をさせるという点では、総合学習のエッセンスを凝縮したようなものだと自画自賛(^^;)しているので、興味のある方は試してみても良いかもしれない。
なお、学習内容としては小学校6年生程度の知識や技能を前提としている。中学生でも面白いし、小5でもできないわけではない。
導 入
- どんな学習活動でも前ふりが大事。これをうまくやれるかどうかで教師の力量は決まる。ここでは新聞の記事を使ってみることにしよう。
- 平成10年8月26日の新聞の1面には、長銀(日本長期信用銀行)の不良債権等に関する記事が出ている。
- 「この頃のニュースには、ずいぶん大きな数が出ているよね。この記事には4兆円って書いているけど、『兆』っていう数、どのぐらい大きいかわかる?」
- (児童)「‥‥‥?」
- 「じゃあ、今日は、そのことを確かめながら、お金のことを考えてみよう」

問題提示
- ここで、何について、どんな答えを求めればよいかを具体的に示す。これをはっきり示せば、あとはちょっとしたヒントを与える程度で、子供はすぐに活動できる。
- 「ここに1円玉で1兆円あるとして、それを1秒間に1円ずつ数えるとしましょう」
- (実際に30秒程、数えてみる)
- 「1兆円を数えるとしたら、どのくらいの年数がかかるでしょう? ちょうど今、『1兆円!』と数え終わるようにするとしたら、何年前から数え始めたらいいのでしょう? 数え始める頃、日本はどんな様子だったのでしょう?」
- 答えは「○○時代の頃」だけでよいのだから、当てずっぽうに予想を言うことはできる。簡単に発表させてから学習活動に入る方が面白い。
- 「第二次世界大戦の頃」
- 「徳川家康が生きていた頃」
- 「聖徳太子が生きていた頃」
- 「縄文時代」‥‥
- いろいろな予想が出てくるだろう。
- (ここまで読んだ皆さんは、いつ頃だと思いますか?)
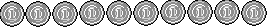
指導上の留意点や準備
- 算数科と社会科に関わる内容なので、年表や電卓が必要になる。これは前もって準備しておく。導入で使った新聞の記事も掲示しておいたほうがよい。(この日の記事には他にも大きな数が使われているものが出ている)
- また、活動は個人でやるよりも少人数のグループでやったほうがよい。学習中に疑問が出て、質問したい場合は、自由に(全体に聞こえるような)大きな声で質問してもよいことにする。(ほとんどのグループが同じような活動をするはずだから、他のグループにも参考になる質問や発言をすることが多いはずなので)
学習活動とその結果
- 実際にやる活動は、それほど難しくない。1兆秒は何年になるかを求め、その時間(年数)を現在からさかのぼるといつ頃になるのかを年表で調べればよいだけである。
- 1日の秒数は「60秒×60分×24時間」で 86400秒になる。これで1兆を割れば日数が求められる。年数を求めるには更に365日で割ることになる。
- 4年に1度は閏年があるので正確には365.25で割るほうがよいのだが、出てくる結果に大きな差はない。でも閏年に気がついて「365.25で割る」という考えを出したグループがあったら、おおいにほめてあげよう。
- さて、1年を365.25日とした場合、1兆秒は3万1688年になる。
- 今から3万年前といえば、縄文時代(紀元前8千年から前300年頃)よりもはるか昔になる。
- 人類が火を使い始めたのが50万年程前だから、それよりはかなり新しい時期ではあるが、まだマンモス狩りなどをしていた頃である。(インディアンなどのアメリカ大陸先住民族が、この頃にアジアから移住して行ったのだそうだ)
- その頃から1円玉を数え続けないと「1兆円」にはならないというのだから、1兆とは途方もなく大きな数であることがわかる。
- ちょっと気のきいた子であれば、「10円玉を数えたとしたら、縄文時代の終わり頃になるね」とか、「100円玉で数えても江戸時代の頃だよ」などと言うかもしれない。これも尊重したい。
- また、新聞の記事を見ながら、「不良債権が4兆円もあるっていうけど、どうして返してもくれないようなところに、こんな大金を貸したんだろうね?」とか、「それでも、元頭取が10億円もの退職金をもらったんだって。1円玉で数えたら30年もかかるのにね」なんていう発言も出るかもしれない。これには静かに頷いておこう(^^;)
本来の「総合的な学習の時間」は、前述したように、「国際理解」「環境」「情報」等について扱うことになるから、このような内容にはならないし、もう少し大きな単元として学習することになる。
しかし、ここに書いた例も、社会科の「歴史」や「社会事象の理解」、算数科の「大きな数」や「時間の単位」などの既習事項を横断的に活用しながら、1つのテーマを追究し、子供の力を伸ばすという点では、総合的な学習と言えないこともない。
さて、ずっと「総合的な学習の時間」と書いてきたが、これは教育課程審議会の答申の中で「一般的な呼称」として使われている言葉で、実際には「各学校の特色・創意を生かした呼称」にすることになる。
そのときに、陳腐な「○○っ子タイム」などという呼び方にしないで、「たのくり」とか「ちゃりんぷりん」とかいうようなわけのわからない名称にしてもらえると、私は楽しい。
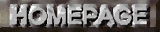 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ