暴漢に消火器を
2001年6月8日に、大阪教育大学附属池田小学校で起きた包丁を持った男の乱入による児童殺傷事件に、私は大きな衝撃を受けた。
教育界でも事件を重く受け止め、さっそくその日のうちに、文部科学省から地区教育委員会等を通して「児童生徒の安全確保について」の緊急指示が入った。
1999年12月に起きた京都府日野小学校の事件の際に、当時の文部省が「幼児児童生徒の安全確保についての点検項目」をとりまとめ、それにそった対応がなされた(子ども110番の家の設置などもその一例である)のだが、今回は、その点検項目を再確認するようにというものだった。
具体的には、児童生徒の登校後は校門を閉める、来校者は職員室に届け出るようにさせる、校内に不審者がいないか巡視する等々なのだが、正直なところ実行が難しく、実行できたとしても今回の大阪のような事件は防ぎえないようなものである。
全ての学校が壁で囲まれているわけではないし、悪意を持った人間が学校を襲おうとするなら、どんな方法を使っても学校に入ってくるだろう。
文部科学省などの上位組織では、「不審者の侵入を予防するように」というような概括的な指示になるのもいたしかたないが、その指示を受け止める側の我々は、自分の学校の実態に応じて、より具体的な対応を工夫する必要がある。
不審者の侵入を防ぐというのは、現実的には不可能である。
来校者には職員室への届け出を義務づけるといっても、本当に凶行を目的として侵入してくる人間が職員室を訪れるはずもない。あまり来校者に警戒的な対応をするようになると、せっかく進められてきた「保護者や地域に開かれた学校」の動きに逆行することになる。
事実、「地域の先生」として、子供たちに畑の作り方を指導している農家の方と話をしたら、「こういう事件があると学校に行きにくくなるなぁ」とこぼしていた。
「学校への不審者の侵入を防ぐ」というあいまいな取り組みではなく、より具体的な対応の仕方を考えておくことのほうが重要だと考える。
(私たちが学習指導の計画を立てるときも、『児童の言語能力を高める』などというぼんやりした目標ではなく、考えられる具体的な事態について、個々の対応法を準備するというのが基本である)
では、どうしたらよいのだろうか?
私なら、自分の学校で同じ事件が起きたらどう対応すべきかということを考える。
学校に刃物を持った人間が入って来て、子供たちに刃物をふるい始めたらどう対応するかを考えるのである。
まずは、その人間の行動を停止させるのが第一だろう。
今回の事件でも、最終的には教職員が犯人を取り押さえたのだが、その間に多くの被害者が出てしまった。刃物を振り回している人間に立ち向かうのだから、危険も大きいし、取り押さえるのも容易ではないだろう。
そこで、私が考えたのは、消火器を使う方法である。

防火用の消火器は、学校のような公的建物には必ず備え付けられている。学校の場合は一般的に2教室に1個の割合で設置されているはずだ。
これを、暴れている犯人の顔に向けて噴射する。
噴射されると視界と呼吸がうばわれるので非常に危険なのだが、殺人を犯そうとしている人間の行動を止めるには最適の方法である。犯人から離れた場所で噴射できるので、素手で組み付いて取り押さえるよりは安全でもある。
消火器の噴射は15秒程度続くから、犯人の行動を止めることは可能だろう。噴射が終わっても、空になった消火器で犯人を叩いたり投げつけたりすることで動けなくなる程度のダメージを与えることもできる。
学校に必ずある消火器を使うのが最適だと思うのだが、他に教室等にあるもので犯人の行動の自由をうばうという方法もあるかもしれない。
例えば、うんちく講座のNo.181「卒業式のアイディア」でふれているのだが、吐いてしまった子への対応のために教室にバケツ1杯の灰を置いておけば、それを使って目つぶしをすることもできるかもしれない。
消火器ではなく、校内消火用の放水ホースもよいだろう。
いずれにせよ、もし自分が学校にいるときに今回の事件と同じ状況に直面したら、どう行動するかを考えておくことが、一番の危機管理策になると思う。
今回の大阪の事件では、野放し状態の危険人物への対応をどうするかなど、他にも考えなければならない問題も多いのだが、私のように学校に勤める者としては、まず自分の学校で同じことが起きたらどうするかを第一に考えるかが先決だと思い、自分のアイディアをまとめてみた次第である。
余談になるが、消火器や放水ホースを暴漢撃退に使うという意識で、その設置場所を事前に確認しておけば、火災発生時の対応としても有効である。
<01.06.10>
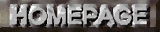 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ