やる気のなくし方
今は落ち着いたのだが、今年度初め頃、むやみに忙しい時期があった。
転任したということもあったのだが、それ以外にも公的・私的な事務局のような仕事が、申し合わせたように集中してきて、数えてみるといちばん忙しかった時期には10個以上の仕事を同時進行していることもあった。
忙しいのはあまり嫌いではないのだが、ちょっと気乗りしない仕事が多く、その時期、私の「やる気エネルギー」はかなり低下したように思う。
少し大げさにいうと、何もやる気がしなくなって、子供ならば不登校になりそうな感じだった。(まあ、それほど深刻ではなかったのだが‥‥)
その頃の自分の状態を振り返って見ると、子供が学習意欲を失うことと、かなり共通する要素もあるような気がするので、自分が子供の教育にあたる場合の参考になる覚え書きとして(あまり面白いハナシではないが)まとめてみようと思う。
1.なんで私がやらなきゃいけないの (動機づけ不十分)
4月頃、私に押し寄せた仕事の中には、自分が望んでもいないのに、立場上やらなければならなかったり、義理ある人から頼まれて、内心は嫌であっても行きがかり上引き受けなければならないものも多かった。
転任した学校の前任者が残して行った事務局(あと2ヶ月だけやれば他の学校に引き継げるというものだったが)とか、前任校では教頭ではなく別の人がやっていた仕事を私がやらなければならないと言われたりすると、「えーっ!そんなことも私がやらなきゃいけないの‥‥」という気になった。(もっとも前任校では私がやっていた仕事を、新任校では別の人がやってくれたりする場合も多かったので、あまり不平は言われないのだが‥‥)
こういう仕事は、やっていても、ついつい不平が心の中にわき上がってきて、気が乗らないことも多い。
子供の場合にも、きちんと動機づけがされて、学習に取り組む意欲が十分であればよいのだが、「自分の将来のためにやっておかなきゃならないのだ!」とか「この時期の○年生は誰でもこれができないといけないんだよ!」と言われるだけでは、やる気が起きないように思う。
2.やり方がわからない (基礎的知識や技能の不足・支援の不足)
私の場合、新しく引き受けた事務局などは、自分で全く未体験で、そのやり方を誰からも聞けずに、自分で過去の資料などを調べて進めていかなければならないものも多かった。
同じ頃に引き受けた県内の町村ホームページコンテストの審査員などは、自分の得意な分野だったので、特別な苦労もなくすいすいこなせたのだが、郡市○○会事務局などというのは、そういう会があったことや、そこで行われている事業についても全く知らないような状態だったので、事務局を担当して事業を進めることになると、一から資料調べをしなくてはならず大変だった。事業を進める前の下調べだけで疲れてしまうような状態だった。
子供の学習を考えてみても、これから行う学習に必要な既習の知識や技能がちゃんと身に付いていないのに、無理に学習に取り組まされれば、私のような気分になってしまうだろう。そういう場合に事前に必要な知識・技能を補っておくとか、学習中に適切な支援を行うとかいうことがなければ、子供は学習につまずき、意欲をなくしてしまうことになる。
3.大変な時期が重なる (複数教科の不振)
やる気がわかなかったり、やり方がわからなかったりということがあっても、それは(大半)自分の仕事なのだし、それでメシを食っているのだから乗り越えて頑張らなくてはいけないのだが、そういう辛いことが同時期に2つ3つと重なると、辛さや不平が先に立って乗り越える気力がなくなってしまうようだ。
子供の学習でも、他の教科の学習は順調だが1教科だけ苦労をしているというのなら、無理矢理にでも乗り越えることができるかもしれないが、数学でも苦労している、理科もそう、さらに英語にいたっては最初からつまずいている‥‥というのでは絶望的な気持ちになるだろう。
こういう場合の乗り越えさせ方は大変だが、場合によっては「○○の教科は今回は学習を免除しよう。まず○○科で追いつけるように集中して頑張ってみよう」というような配慮も必要かもしれない。
4.成就感がない (スモールステップの不足)
私が担当した多くの仕事は、中には6月頃に終わってしまうものもあったが、大半は8月末ぐらいに本番があるというものが多かった(もちろん1年間やりとおさなければならないものもあるが‥‥)
いちばん気力が落ちた5月頃には、忙しく頑張っていても、その時点では仕事の完成をみないというものが多かった。
現時点(9月)では、8月末ぐらいにその仕事を終えて、それなりに成功し、他の人たちから「佐々木さんの頑張りのおかげでうまく行きましたね」と言われると、いやいや取り組んだ仕事であっても心地よい成就感を持っているのだが、まだ仕事の途中である5月・6月頃には、「いくら頑張っても先が見えない。やればやるほど仕事が増えるような気がする」という暗い気持ちになることが多かった。
子供の学習においては、なるべく短期間で成就する目標を設定し、そのステップごとにやり遂げた喜びを感じさせるような配慮をしないと、意欲が長続きしないように思える。
5.環境が変わる (環境への不適応)
グチを言ってもしょうがないのだが、今年引き受けたいくつかの仕事の中には、「私が転任していなかったら、もう少し手際よくこなせただろう」と思うものも多かった。
転任したことで、いろいろと環境も変わった。卑近なところでは職員室で使っている私物のパソコンの環境も新しく設定しなければならなかった。ネットワークの設定変更、職員室のプリンタを使うための調整等々。3月までの仕事の環境と同じ程度に調整するにもだいぶ時間がかかった。
転任していなければ、そういう労力が不要で仕事ができたはずである。
また当然のことながら、転任によって職場の人間関係も変わる。現任校の職員の方々は、皆、有能で良い人ばかりだし、私もあまり人見知りではなくどちらかというと人に慣れるのははやいほうなのだが、それでも新しい環境に慣れるにはちょっと時間がかかる。
人だけでなく、その地域・学校での仕事の進め方の約束に馴染むのも、それなりに大変だ。(余談になるが、前任校では職員室でくわえ煙草で仕事をしていた私にとっては、職員室が禁煙で別室で喫煙しなければならないのもちょっとストレスであった。反対に煙草を吸わない人が煙の立ちこめる職員室で仕事をしなければならないということになってもストレスになるだろう)
前の環境で「あいつだったら、これくらいの仕事はできるだろう」と思われていても、環境が変わったばかりのときに同じことを期待されてもそれに応えることは難しいかもしれない。ましてそれ以上のことを期待されるのでは重荷になることもある。
子供の場合にも、学級の編成替えがあったり担任が替わったりという環境の変化があれば、前と同じような力を発揮することが大変になることもあるかもしれない。学級の状態だけでなく、家族の構成の変化があったなどということも大きな要因になる。
ましてこれまで述べたように、同時期に辛いことが重なったとか、苦労する要素が増えたなどということになれば、その時期に学校や家庭の環境が変わることは、子供にとってやる気を失わせる大きな要因になる。そういう背景がある子供には、教師も十分に注意を払わなければならないだろう。
6.好きなことにもやる気がなくなる (意欲喪失の全般化)
こうやって忙しく辛い時期が重なって、自分の意欲がなくなった時期、ふと自分の生活を振り返って見ると、面白いことに気がついた。
ちょっと嫌な仕事にやる気がなくなると、前までは自分が好きでやっていたことにも意欲がなくなるのである。
私が好きでやっていることといえば、はっきり目に見えるのは自分のホームページの更新である。普通の時期であれば眠る時間を惜しんでもやるのであるが、この時期(今年度の4〜7月頃)は目に見えて更新が少なくなっている。
忙しくて時間がなかったこともあるが、ホームページの更新をする時間が全くないというほど忙しかったわけでもない。この頃はかなり落ち込んだ気分のまま、それを紛らすために、(私のもう一つの趣味でもある)パチンコで漫然と(生産性なく)時間をつぶしていることも多かった(^^;)。(まあ、そうやってなんとか自分のバランスをとれるところが私の長所でもあると思っているのだが‥‥)
子供の場合、1つのことで成功して成就感を味わうと、他の方面にもそれが波及して、学習全般に対する意欲が増すということもある。しかし、私の例のように、いくつかのことでやる気がなくなると、それが生活全般に影響し、本来得意だったことにも意欲がなくなるということもあるだろう。
「あいつは数学ではつまずいてやる気をなくしているが、得意な野球では頑張っているから、いずれは数学にもよい影響が出るのではないか」と期待するのもいいが、場合によっては野球もダメになってしまう危険性をはらんでいることを十分に注意すべきだし、実際に(この例では)野球がダメになりかけているとすれば、その元凶になっているものに目を向ける必要があるだろう。
乗り越えるには
こういう状態におちいって、生活全般がダメになる可能性も大きいのだが、私の場合はなんとか乗り切れたような気がする(^^;)
ダメな状況については分析をしたので、乗り越えられた状況についても何かの参考になるかもしれないから、2つほどまとめてみよう。
1.時間が解決する
今、私の状況が落ち着いたのは、忙しい原因になっていた多くの行事が終わってしまったからである。それらの行事は8月がピークだったが、終わってしまえばあとは苦労することもない。
終わった結果については、全てに満足できるわけではないが、やろうと思っていた仕事が間に合わなかったとしても、それはそれなりになんとかなるものである(^^;)
その時刻がくるまでは、あれこれと思い悩んだりもするが、まあ、その時刻が過ぎさえすれば悩みも消える。楽天的になることも必要であろう。
ただ、子供の学習の場合は、数ヶ月の短期間で終わりということもないので悩みが長く続くということが多い。前述したスモールステップの導入などで、短期間で解放感を与える配慮が必要かもしれない。
2.別の価値観を持てる場所
あることが嫌になって、それが生活全般に影響し、好きだったことさえもやる気がなくなるというのは前述したとおりだが、ここでいう「好きなこと」というのは、まだ仕事と同一のレベルのものである。
つまり、それに費やす時間が必要で、そのための労力も必要であり、結果もなんらかのかたちで残るというようなものである。
こういうタイプの活動は、多忙などの理由で時間がなくなればできなくなることもあるし、活動全般についての意欲がなくなれば、その影響でやらなくなってしまうこともあり得る。
うまく使えば、もう一度やる気を出させることにも役立つが、思うようにいかないことも多いだろう。
やる気を復活させるには、そういう活動とは全く別な価値観の体験を重視するのがよいかもしれない。自分のことを振り返ってみれば、なんとかやる気を維持することができた要因は、家族との触れ合いだったようにも思う。
これは、特別に時間や努力を必要ともしないのだが、仕事で行き詰まったり悩んだりしている自分に、「そんなこと、たいしたことじゃないよ」と思い直させる力を持っていると思う。
私の場合は、それが家族だったのだが、人によってはまた別のものがその役割を果たしてくれるということもあろう。いずれにしても何かに行き詰まったり悩んだりしているときに、それとは別の視点で、「今悩んでいることだけが人生の全てではない」と気づかせてくれるものがあれば、本来の自分を取り戻し、スランプから脱出できるのではないかと思う。
子供が学習や学校生活で行き詰まったときに、何に頼ったらそれを打開できるかというのは、それぞれの状況によって違うだろうが、そういうものを見つけだそうとする視点が必要だと考える。
まあ、あれこれと書いてきたが、一度やる気がなくなってしまうと、それを元に戻すのは難しい。しかし、生きていくには自分の力でなんとか乗り越えていくことが大事だと思う。
やる気の出させ方ということでは、うまい方法を見つけられないのだが、やる気のなくし方なら、私がこれまで述べたような状況を与えれば簡単なことだと思う‥‥(^^;)
<01.09.10>
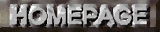 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ