授業にブラウザを使う
私は、この地区の教職員のパソコン研究委員会のメンバーで、今年は年功序列か委員長になったが、ずっと郡市教職員パソコン講座の企画と指導を担当している。
平成9年度は「ホームページの作り方講座」と題して、HTML文書の作り方を指導したが、参加した先生達が異口同音に話したのは、「これは学習指導に使える」ということだった。
私もHTMLを勉強し始めた頃から感じていたことであるが、インターネットに使われるHTML文書とブラウザソフトは、学習指導に使っても実に効果的であると思う。
パソコンが学校に入ってきた昭和60年代、学校でのパソコン利用といえば、教師が指導する内容をコンピュータに代行させるCAIが主であった。当時はコンピュータをいじれる教員のほとんどは自作ソフト派で、BASICやC言語でプログラムを作る人が大半であったし、そうでない場合は、いわゆるオーサリング・ソフトを使って、紙芝居めくりのような「学習ソフト」を開発するというのが「パソコンの教育利用」の代表的形態であった。
現在は、パソコン本来の(一般社会で使われているような)ワープロとか描画とかデータベースといったような使い方を活用させるというのがメインになってきているが、それでも過去のオーサリング・ソフトのような使い方も重用されている。
教師の指導をパソコンに代用させるという場面でも使われているし、児童生徒の表現手段としても効果があるからである。
ところが、そのためのソフトというのは、けっこう使い勝手が悪い。富士通の「絵本ライター」等は、機能が低いし、かといってマクロメディアの「ディレクター」あたりは難しすぎる。
それらよりももっと簡単に高機能なマルチメディア表現と、自由な学習コースの分岐ができる処理を扱えるのが、HTML文書と、それを扱うブラウザソフトである。(ホームページを作った方にはすぐにご理解いただけることと思う)
めんどうなプログラムを組まなくても、静止画像・動画・音声などのマルチメディア資料は扱えるし、リンクの使い方の工夫によって、分岐のある学習コースの設定も容易である。また、既製のオーサリングソフトやプレゼンテーションソフトのように、独自の資料ファイルを作らなくても、それこそ世界中のサイトから収集できるデータをそのまま扱えるし、場合によっては自分でダウンロードしてきて資料として準備しなくても、環境が許せばそのサイトのURLを埋め込むだけで資料の活用ができる。
これを学習指導に使わない手はない。児童生徒用のクライアント機が直接インターネットにつながる恵まれた環境にある場合だけでなく、スタンドアロンのパソコンにあっても、HTML文書とブラウザをうまく使うことによって、様々な効果的な学習指導が可能であると考える。(ネットワークやクライアントからのインターネット接続ができれば更によい)
ただ、そのために欲しいと思うのは、児童生徒のためのブラウザソフト、及びホームページ作成ソフトである。
Internet ExplorerとNetscape Navigatorは、それぞれ急速な進歩を遂げ、高性能化が進んでいるが、児童に使わせるには適当でない。学校現場で欲しいのは、基本性能を確実に押さえた上で、児童生徒に不必要な機能を全てカットしたブラウザである。できればアダルト系統の情報は最初からソフトとしてカットする機能などは備えていてほしい。また、児童生徒からの情報発信も今後重要視されるだろうから、ホームページ作成ソフトも子供に使えるようなものが欲しい。
このページをご覧のソフト開発業者の皆さん(いないかぁ)。このジャンル、絶対に将来有望ですよ。(小学校高学年以上が使えるようなものです)
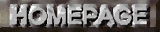 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ