地球より重い命の説明法
ご存じのように、先日、長崎市で、4歳の幼児が中学校1年生の12歳の少年によって殺害されるという痛ましい事件が起きた。
その年頃の子供たちを扱う私たち教育関係者にとっては、大きな衝撃である。
この事件の背景には様々な要素があるのだろうが、マスコミ報道しか情報がない私が、この事件についてあれこれ言うのは適当ではないかもしれないので、ここでは触れないことにする。
ただ、こういった事件の再発を防ぐために、子供たちに生命の大切さを理解させることは、教育に携わる者にとって大事なことである。
基本となるのは、毎日、直接、子供たちに触れる学級担任の指導であるが、今回のように重大な事件が起きた場合には、全校集会等の場で、校長や生徒指導担当者がそれに触れた話をすることもあるだろう。
そのような場合、よく使われるのが、「一人の人間の生命は、地球よりも重い」という表現である。
生命の大切さを訴えるときに常套句のように使われる表現であり、今回の事件でも新聞報道等で何度か目にした。
しかし、この「地球よりも重い」という表現、どのくらい、子供の心に響くのだろうか?
私が子供の立場なら、「そう言われても、俺、地球を持ったことないからわかんないや」と思ってしまう。ちょっと性格がひねくれているせいかもしれないが、本来、こういった講話は、(事件を起こしそうな)ひねくれている子供に特に訴えるようなものでなければいけないはずである。
講話をする校長や生徒指導担当者は、常套句である「人間の生命は地球よりも重い」という表現で講話をすることで、「私もひととおりは生命の大切さを訴える講話をした」という自己満足ができるかもしれないが、私に言わせてもらえば、そんな講話は上滑りで何の工夫もなく、効果は期待できない。
生命の大切さを、聞いている子供たちに心の底から納得させるには、講話をする側も、必死に考えて工夫をしなければならないのである。安易に常套句を使って「おしまい」というのでは職務怠慢だと思う。
では、どんな方法を使えばよいのだろうか。
まあ、講話をする人がそれなりに工夫をすればよいことなのだが、私は次のような方法を考えてみた。
まず、紙を3万枚準備する。
紙の種類は何でもよいのだが、その後の使用を考えると、コピー用紙がよいかもしれない。
紙の単価は、B5サイズなら1枚で2円弱、A4サイズなら1枚2円強である。(安売り店等で格安に仕入れた場合)
学校にそれだけのストックがあれば好都合なのだが、たいていは無理な話なので、学校事務の担当者に相談して、年度内の予算で揃えられるならば無理を言って揃えてもらう。これもほとんどは無理だと思うので、学校出入りの文具業者に頼んで現物を貸してもらうのがよいかもしれない。
それも無理なら、講話をする校長が自らのポケットマネーで買ってもいいだろう。B5サイズの3万枚なら5万円ちょっと。この紙を全部自分で使い切れないから、2割引の4万円ぐらいで誰かに売ればよい(^^;) それでもマイナスは1万円程度だから、自分の学校の子供たちに生命の大切さを訴えるための費用と考えれば安いものである(^^;)
さて、3万枚の紙が揃ったら、全校集会で次のような話をしよう。
まずは、その紙を1枚だけ取り出して、子供たちに見せる。
そして次のように話す。
皆さんは日記を書いていますか。書いている人なら、この紙に1枚ぐらいは書けますよね。
さて、毎日、この紙に1枚ずつ日記を書いたなら、私たちは一生のうちにどのくらいの日記を書くことになるでしょう?
そこで、あらかじめ頼んでおいた職員に、例の紙を持って来てもらう。
日本人の平均寿命は、80.6年。日数にすると「365×80.6+40(閏年分)」で29459日。約3万日である。
前述のコピー用紙の場合、1枚の厚さが約0.1mm(正確には0.093mm)ので、100枚なら1cm。1万枚で1m。3万枚なら3mとなる。
頼んでいた担当者に、その紙を壇上に積み上げてもらう。縦に積み上げられるならば3mの高さになる。これはかなり難しい作業なので、校長が話をする演壇に乗せてもらってもよい。6列に積み上げて、それぞれの列の高さが50cm。これでもそのボリュームは子供たちにかなりのインパクトを与えるだろう。
そこで、次のように話を続ける。
これが、日本人の平均寿命の80.6歳の人が、一生の間に書く日記の紙です。
もし、こんなに長い小説があったとしたら、皆さんは読もうと思いますか?
(たぶん、子供たちは首を横に振ると思う)
でも、この中には、とっても大事な日のことを書いた紙もたくさんあります。
例えば、小学校に入学した日のこと。あるいは6年生の修学旅行の日のこと。そして、これから先のあなたの結婚式の日のこと。あなたの子供が生まれる日のこと。
(時間に余裕があれば、それらの例文も紹介できればよい)
1日1枚の日記にしただけでも、人間の一生は(紙を指し示しながら)こんなに長いのです。
この人間の一生を、誰かが勝手に台無しにしてよいはずはありません。
今回の事件で殺された長崎の駿君の一生は、たったの4年間でした。
(紙の中から14cm程を取り出す)
普通に生きていたなら(紙全体を指し示しながら)こんなに生きていれらたはずの駿君の一生は、結婚式のページどころか小学校の入学式のページの日記も書かれることなく、こんな短い間で終わってしまったのです。
駿君を殺した中学校1年生の少年にしても(紙の中から44cm程度を取り出しながら)これまで生きてきたのはたったのこれだけです。あとの人生は(ここで積み上げた紙を全て払い落とすパフォーマンスがあってもよい)「人殺し」「人でなし」の汚名を来たまま、あるいは他の人が言わなくても自分でそう自覚したまま生きていくしかありません。少年が今後、人並みな幸せな人生を過ごすことはできません。彼自身がそれを絶ってしまったのです。
「だから皆さんも」というようなつや消しの講話は必要ないと思う。講話はここまででやめるべきであろう。それでも「人間の生命は地球よりも重い」という講話よりは効果が大きいはずである。
使った紙は、1日か2日の間、子供たちの目につくところに置いてもよいかもしれない。
この方法がベストということでもないので、講話をする人それぞれが、子供の心に響くような話を工夫すればよいと思う。ありきたりの表現でなく、自分で一生懸命考える努力をすべきだと思う。
ここからは余談めいてしまうが、「人を殺したら幽霊が出てくる」という話も、子供に「人殺しはしてはいけない」と強く思わせる方法としては有効だと思う。
もし人殺しをして、それが誰にもばれず、普通の生活を続けることができたとしても、殺人者は死者の幻影におびえるだろう。夜、ひとりで鏡を見ることができないかもしれない。鏡の中の自分の背後に幽霊がいるかもしれないという恐怖があるからだ。
この世に幽霊というものが現実に存在するということは、教師として子供たちに教えることはできないが、殺人者の心の中には幽霊は存在するということは言えるだろう。現実には幽霊が出てこなくても殺人者は幽霊が出てくる悪夢にうなされるはずである。
たとえ誰が裁かなくても、殺人者は殺人という事実の記憶と自らの良心によって、その後の人生が苦渋に満ちたものになることを余儀なくされる。これは宗教で言えば「誰も見ていないと思っていても神が全てを見ている」ということであろう。このことは子供でも共感できるのではないだろうか。
「自分の良心だけはごまかすことができない」という倫理観を、子供のうちから育てておかなければならない。(実際に犯罪を犯す人間には、この倫理観が欠如しているのだとは思うが‥‥)
宗教が生活に根付いている国なら、「良心=神」という図式で、強力な倫理観を持たせることもできるだろうが、日本は基本的に無宗教の国である。だからこそ、せめて「人殺しをしたら幽霊に取り憑かれる」ような話は、小さい子供のうちから教えておいたほうがよいのではないだろうか。
<03.07.14>
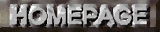 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ